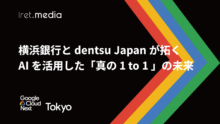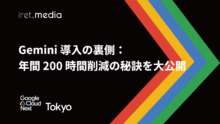はじめに
【Google Cloud Next Tokyo 2025】のブレイクアウトセッションの1つである「GeminiとAgent Development Kitで創る!AI Agent開発の最前線」に参加してきました!
セッションは、「AI Agentとは」といった基本的な部分から、「開発」といった実用的な部分までご紹介頂くものでした。
本記事は、そのセッション内容についてのレポートです。
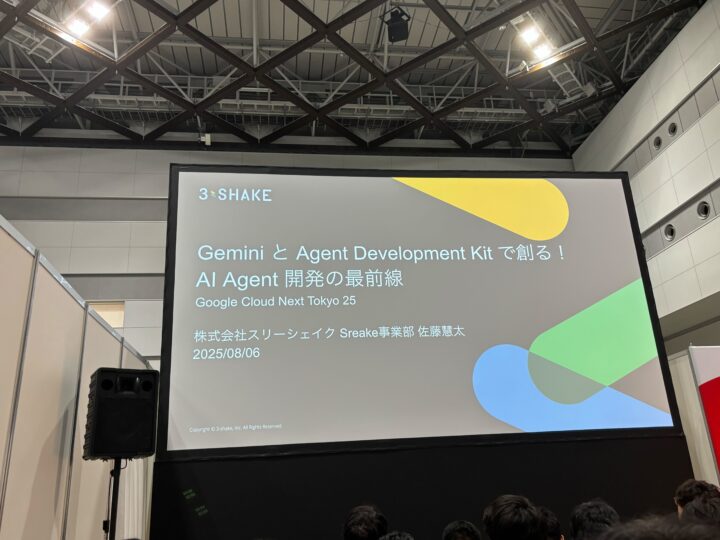
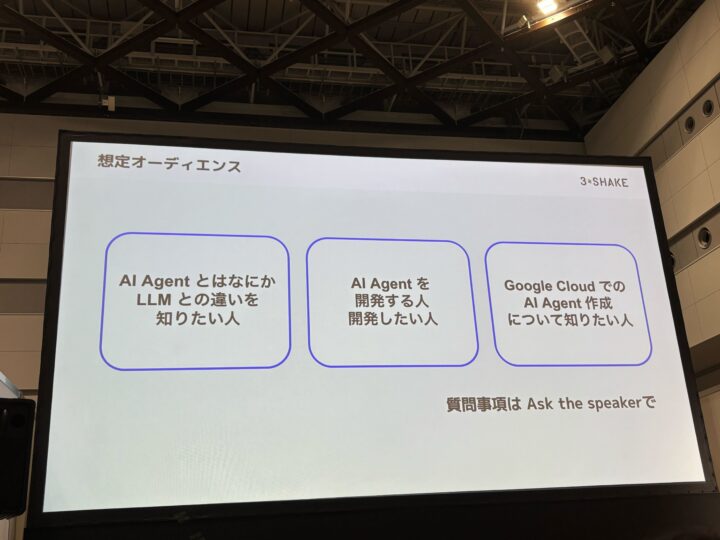
AI Agentの定義
「AI Agentとは」と言う問いに対する回答は企業によって異なるようです。
とはいえ、タスクを完了させるシステムというのは間違いなさそうです。
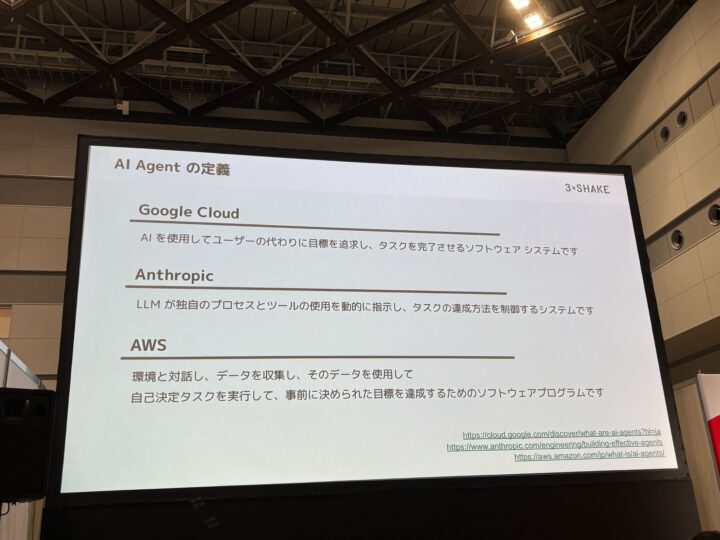
12 Factor Agents:大規模言語モデル(LLM)を活用したエージェントを、ソフトウェアとして高い信頼性を持って運用するために不可欠な、12の重要な指針
初見でかっこいいネーミングだなとしか思っていなかったんですが、エージェントを運用する上で大事な指針だそうです。
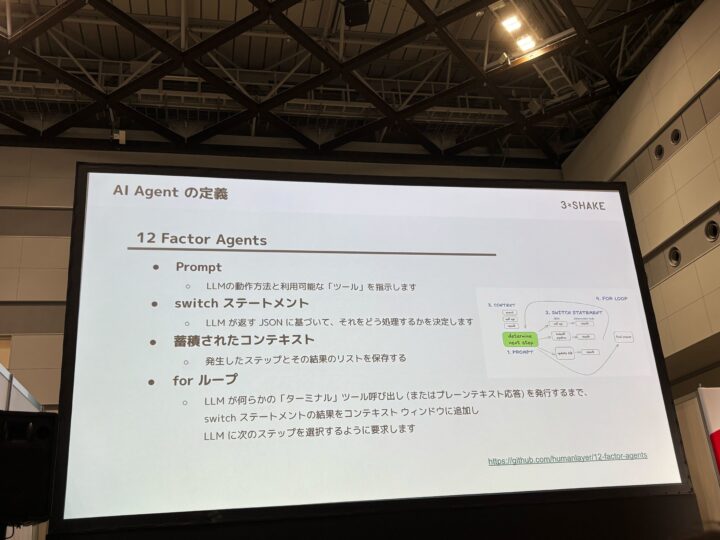
BotやAI Assistantの違いを触れて頂き、AI Agentについて理解が深まりました。
自立的に動く、、まさにエージェントで、すごいとしか言えません!
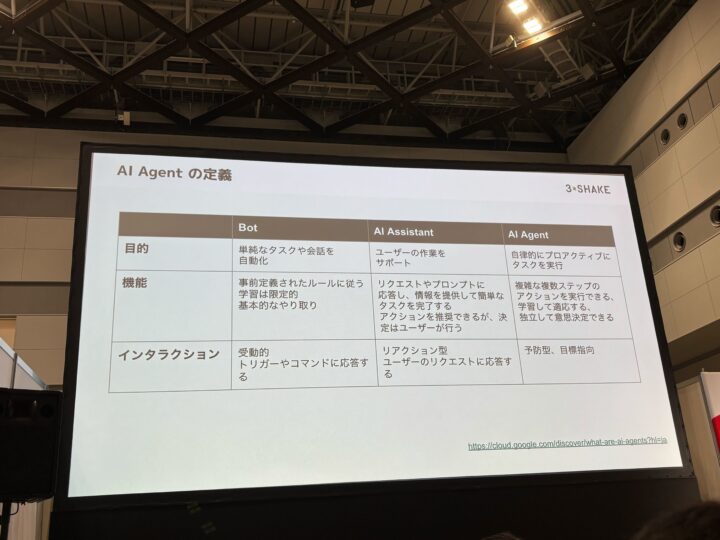
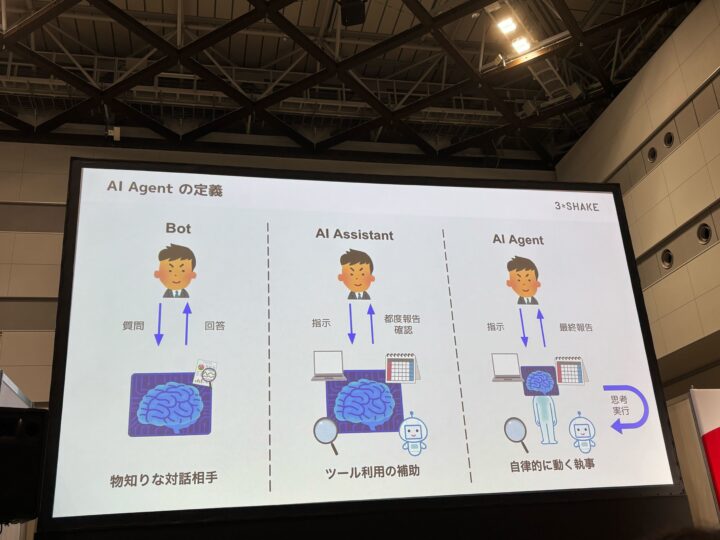
AI Agentを作る
AI Agentを構築方法として、ノーコード、ローコード、フルコーディングがあります。
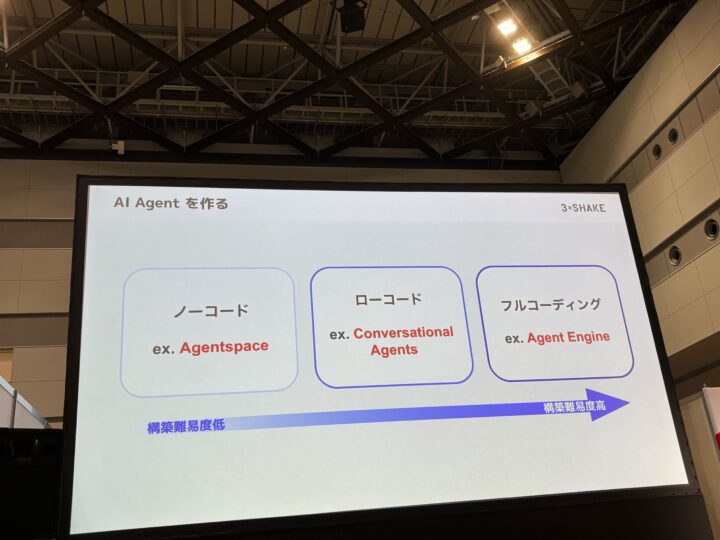
ノーコードの特徴
- コードを書く必要がないので構築がしやすく、メンテナンスコストが低い
- 構築がしやすい分、複雑なものが作れないなどの制限あり
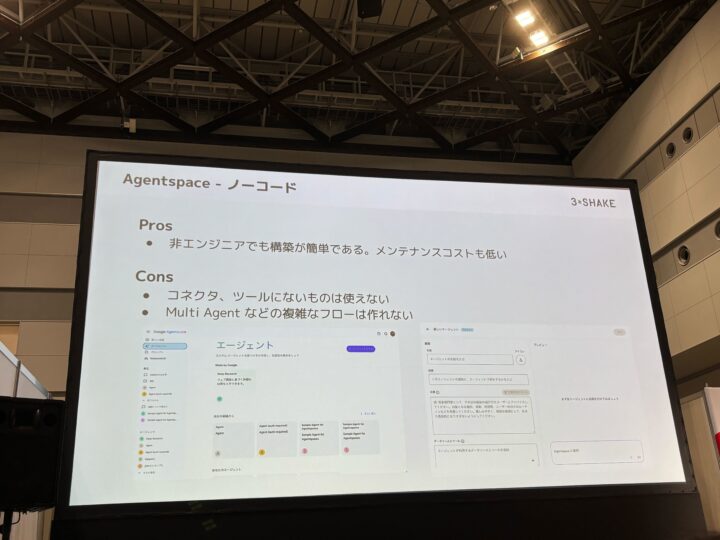
ローコードの特徴
- コードを書く分、柔軟性を得られる
- Conversational Agentsと仲良くなる必要あり
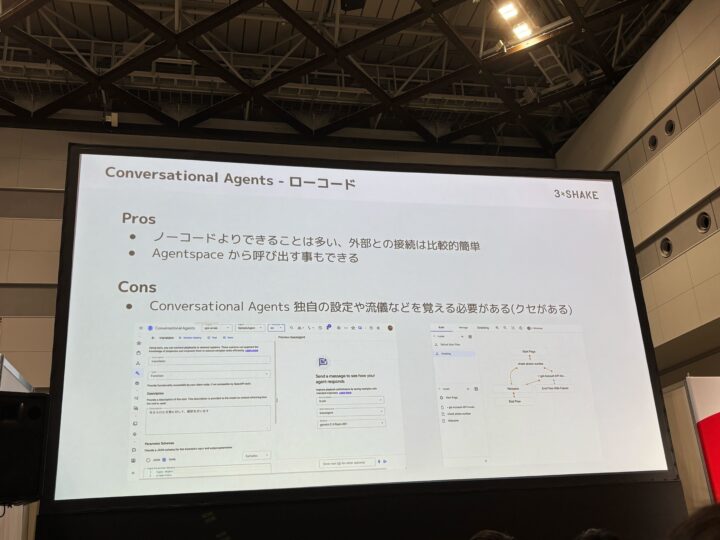
フルコーディングの特徴
- 全てコードを書く分、柔軟性も高く、運用面でサポートが厚い
- O11y(Observability):「可観測性」を意味し、 いつ、どこで、何が、なぜ起こっているのかを観測・理解できる能力
- 余談:これでオブサバビリティと読むそうで、「Observability」のOとyの間に11文字あるからだそうです。
- O11y(Observability):「可観測性」を意味し、 いつ、どこで、何が、なぜ起こっているのかを観測・理解できる能力
- Conversational Agentsと仲良くなる必要あり
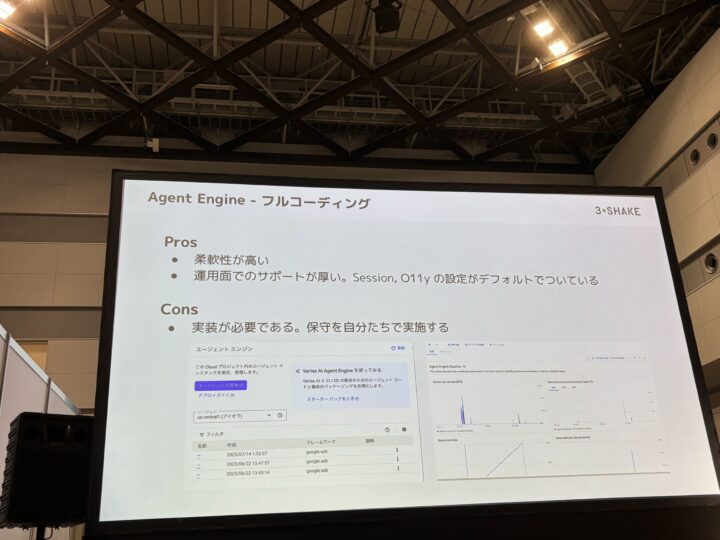
Agent Development Kit
Agent Development Kit:AI Agentを作るためのフレームワーク
7月時点では1.7.0だったそうですが、当時時点で1.9.0が出ていたようです!
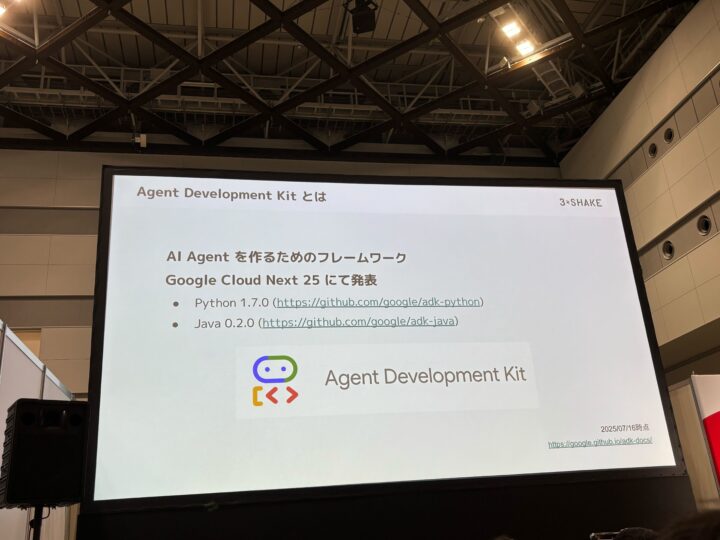
Agent Development Kitは、Agentの構築だけでなく、様々なツールが利用でき、便利そうです。
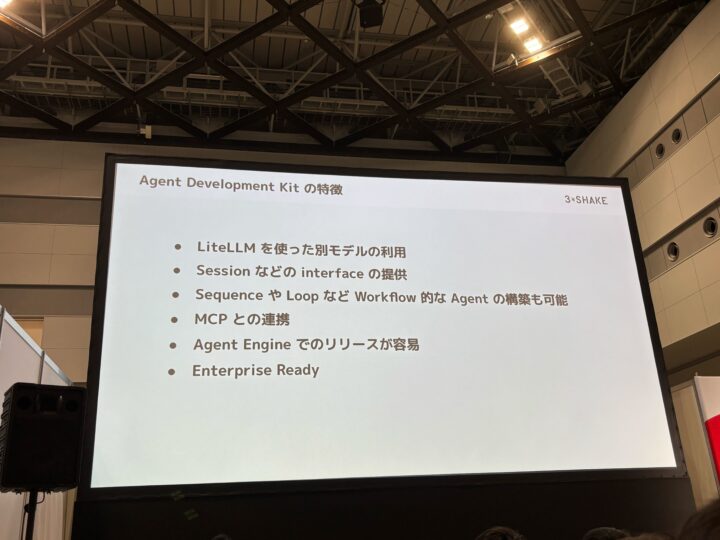
デプロイ環境は色々あり、とっつきやすいのはAgent Engineですが、Agent2Agentの実行時間が限られるそうです。
Agent同士で何か複雑なことをして欲しいようなら、Cloud Run Serviceが良さそうです。
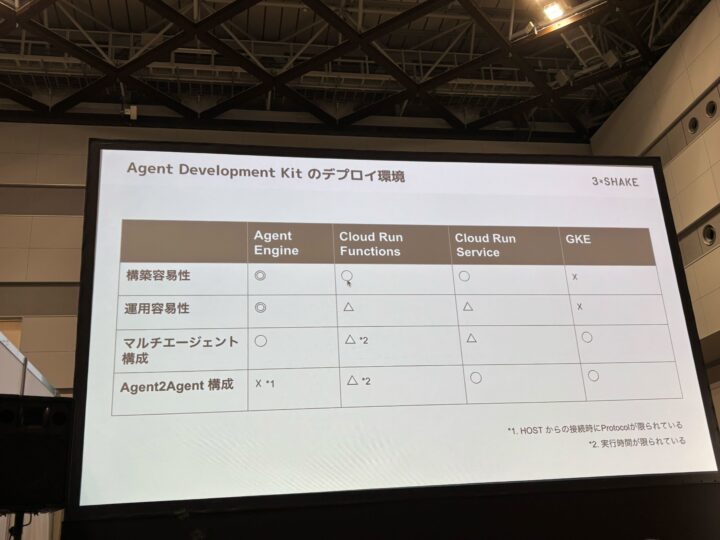
Agent Development Kitの構築について、具体的なコードを見せて頂きました。
実際に手を動かしたことのない中の感想ですが、toolsがAgentの賢さを左右するなと感じました。
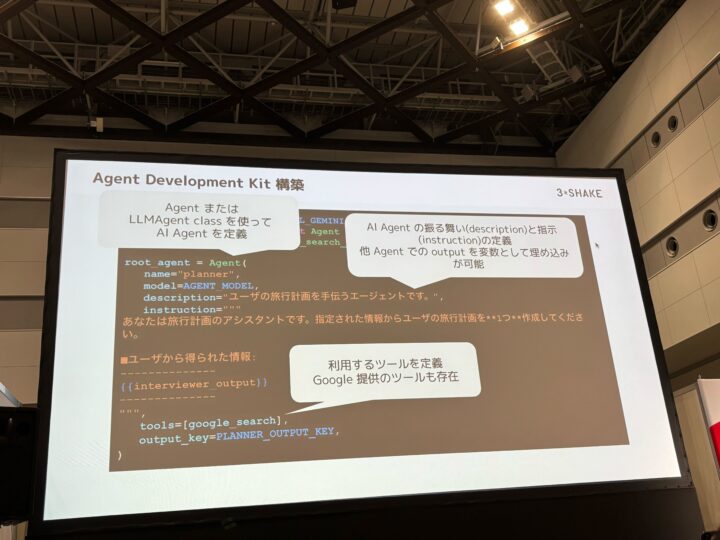
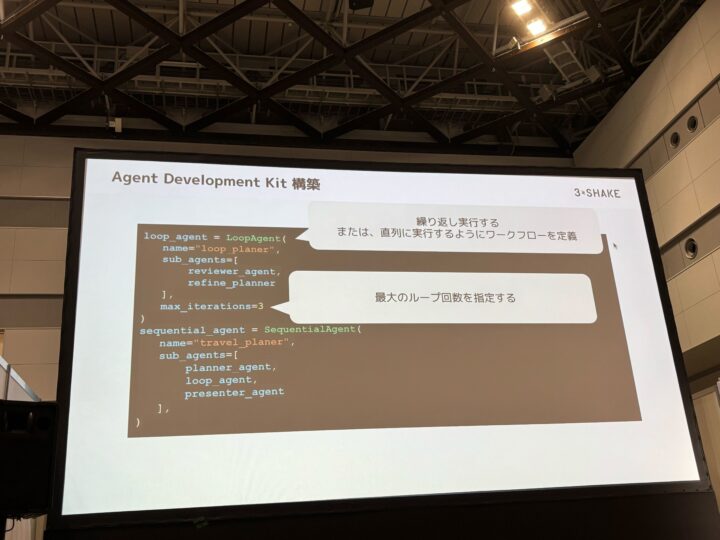
デプロイ環境は色々ありますが、基本的にはGoogleのサービスにデプロイするか、コンテナとしてデプロイするかの2パターンです。
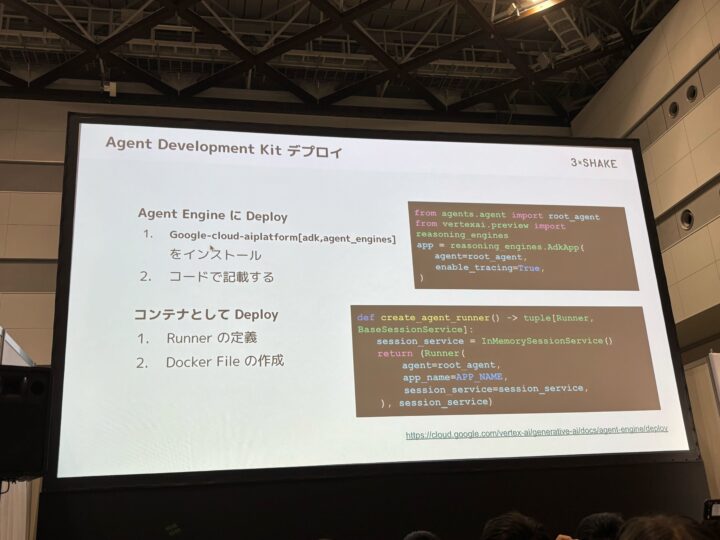
AgentをToolとして利用すれば、Google 提供のToolsに制限がなくなるというTipsを紹介いただきました。
また、__init__ .pyを使いRoot Agentを閲覧できるようにすることで、様々な環境で動かせるようになります。
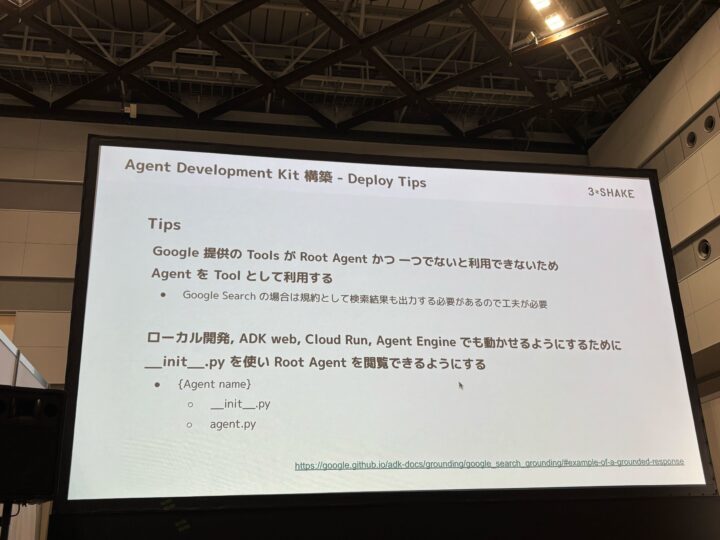
テストの指標として、「何が成功なのか」、「何をして欲しいのか」、「どう評価するのか」が挙げられました。
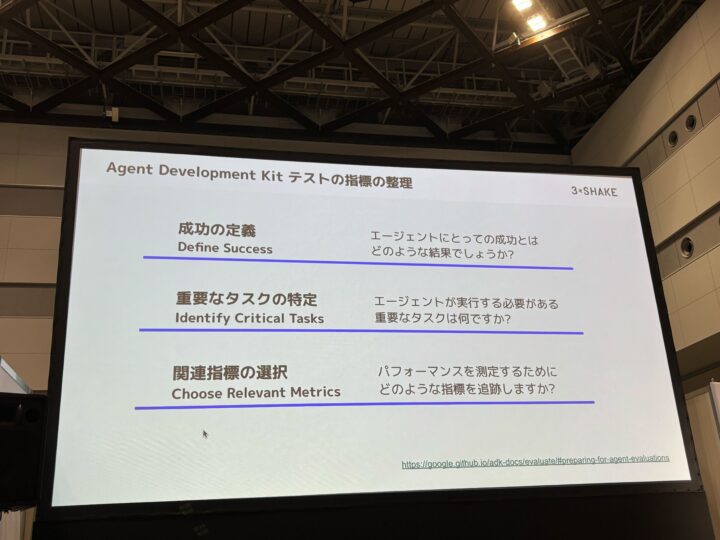
テスト観点として、「エージェントの解決への手順」、「最終出力の品質、正確性の評価」が挙げられました。
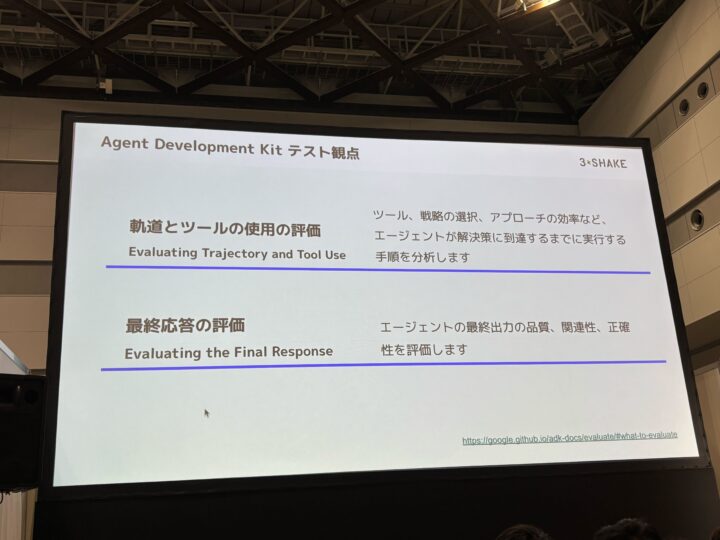
Agent Development KitのテストはJSONを作成したり、Pytestを作成したりして、テストするようです。
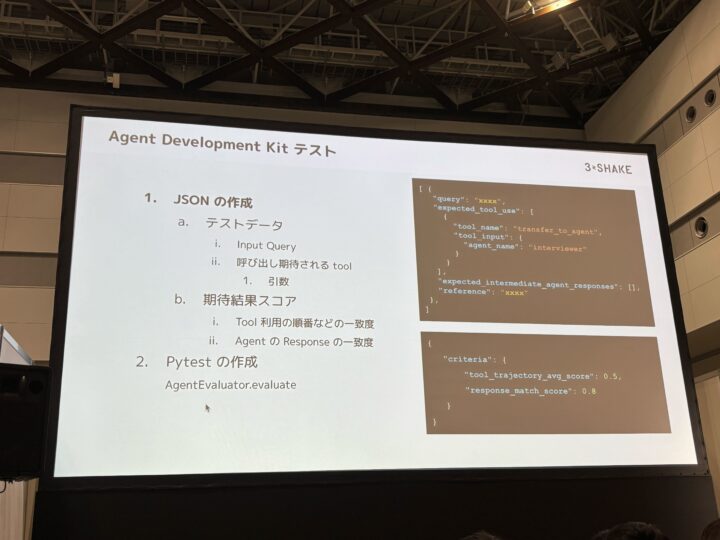
ADK webでは、作成したJSONを配置することで、実施できるようです。
Tipsとして、AgentのフローをJSONとして出力し、テストデータとすることで、かなり楽にテストできるようです。
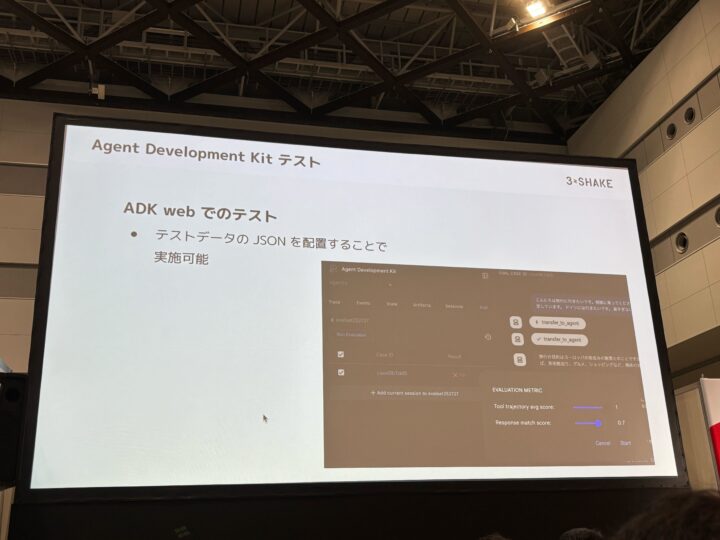
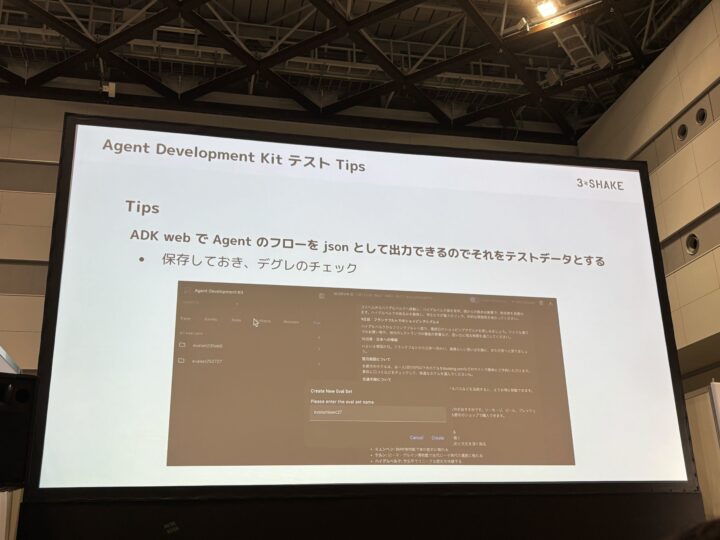
可観測性の視点として、UX起因、SLI/SLOがあり、どちらも目に見えにくい部分です。
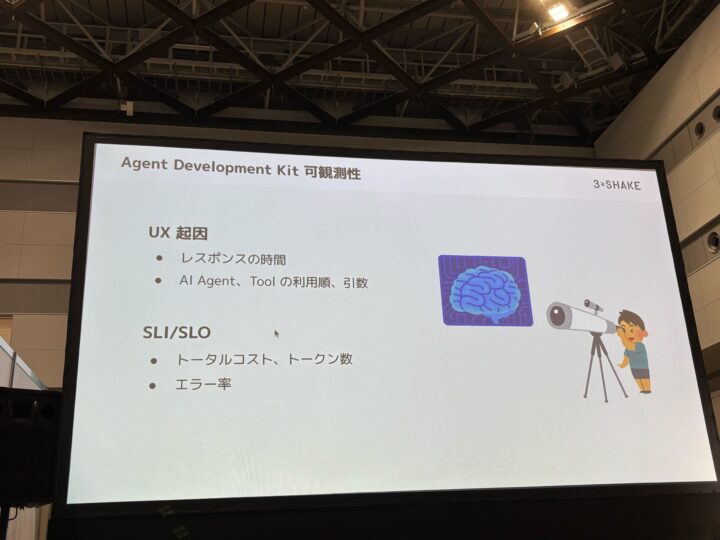
google-adk[eval]をインストールすることで、ADK webのEventで見えにくい部分が見えてきます。
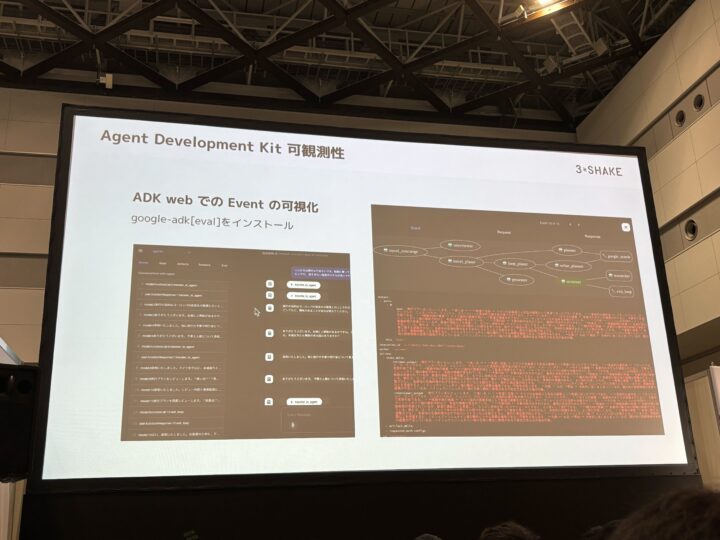
- otel(OpenTelemetry):テレメトリデータを生成、処理、送信するのを可能にするオープンソースのオブザーバビリティフレームワーク
- tracerは処理の記録をするものだが、快適性を損なったり、邪魔な記録が増えたりすることがあるため、NoOpTracer(No Operation Tracer)にすることがある
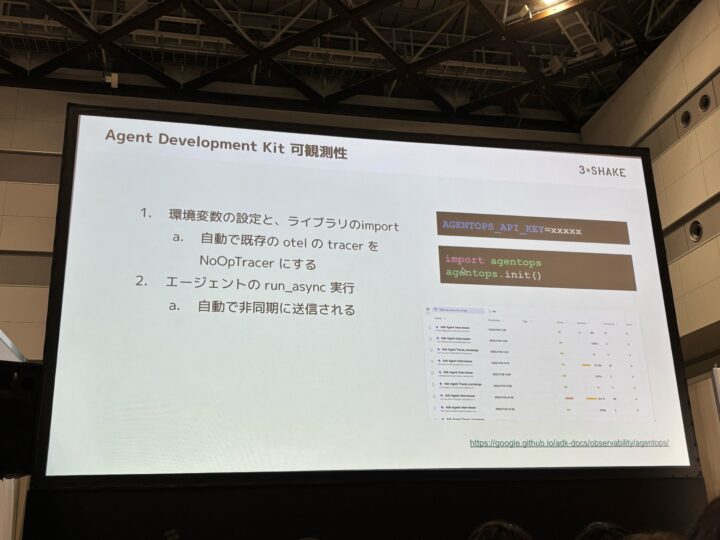
ツールとして自作関数を使うとエラーが出てAgentが動かないため、ラップする必要があるそうです。
このエラーに3時間くらい掛けたと仰ってたので、かなり有益なTipsかもしれません。
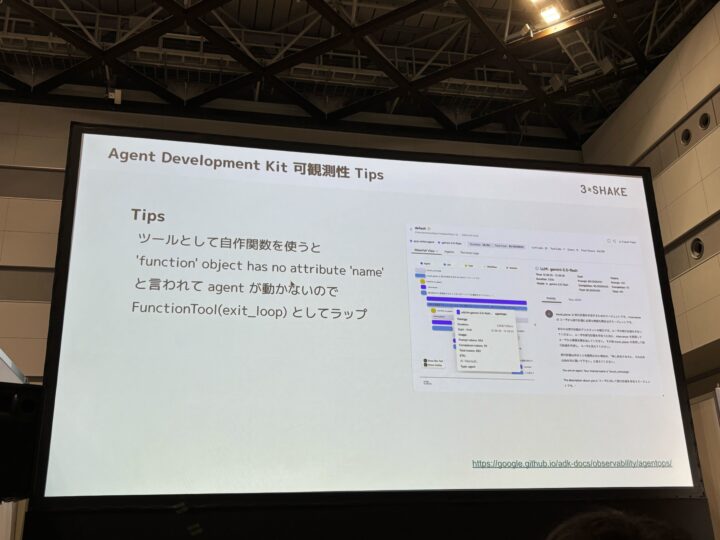
おわりに
セッションを通じて、「AI Agentとは何か」という基本的な部分から、AI Agentの開発方法まで学ぶことができました。
AI Agentが自動でタスクをやってくれれば、「猫の手も借りたい」なんて言葉は死後になるかもしれません。
とは言えこれを実際開発するとなると難しそうだなと感じたので、Agent Development Kitについて知る必要があります。
いつかAgentも当たり前になると想像すると、ワクワクする部分もありますが、使いこなせるかという不安も残ります。
AIの進化の凄さと、今後について考えさせられるセッションでした!
参考資料
iwashi.co, https://iwashi.co/2025/07/06/12-factor-agents, (2025/8/12)
NTT docomo Business, https://www.ntt.com/business/services/xmanaged/lp/column/observability.html,(2025/8/12)
elastic, https://www.elastic.co/jp/what-is/opentelemetry, (2025/8/12)