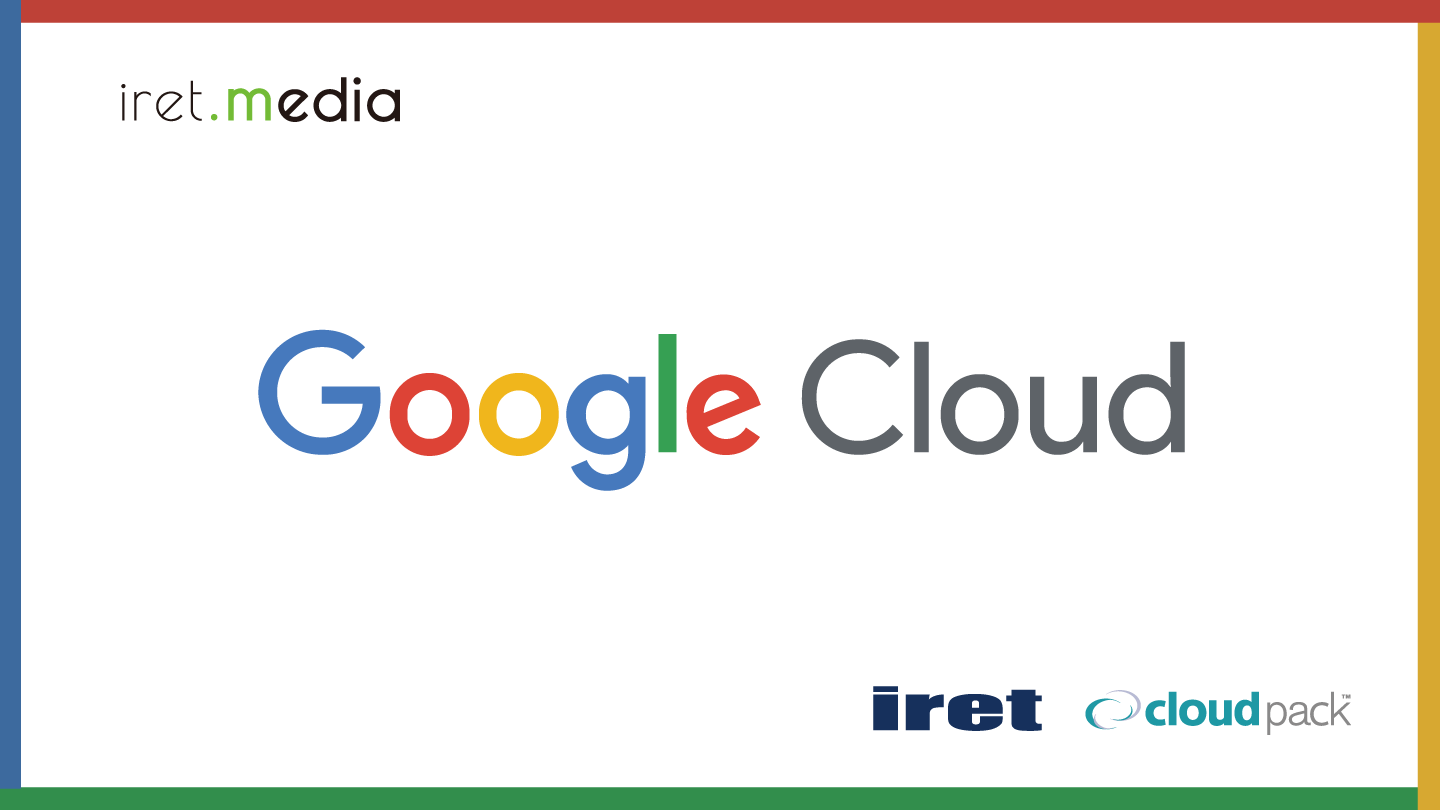Professional Data Engineer試験の勉強をしていると、Apache FlinkとApache Beamの名前が両方出てきて混乱しがちです。どちらもストリーム処理を支えるOSSとして知られていますが、Google Cloud の世界では「DataflowはBeamで動く」と説明されるため、Flinkとの関係が分かりにくいのです。私自身も試験対策中に「FlinkでできることとBeamの役割はどう違うのか?」と迷いました。本記事では、その違いと対応関係を整理し、試験で判断を誤らないためのポイントを共有します。
FlinkとBeamが混乱を招く理由
- どちらも「ストリーム処理のOSS」と紹介される
- 両方に「ウィンドウ」「トリガー」など似た概念がある
- Google Cloud のDataflowはBeamランタイムだが、他のクラウドではFlinkが選ばれることもある
試験では「DataflowはBeamを使う」と理解していれば十分ですが、背景を知らないとサービス選択問題で迷いやすくなります。
Apache Flinkの役割
ネイティブなストリーム処理エンジン
Flinkはリアルタイム処理を得意とする分散エンジンで、状態管理・低レイテンシ・イベント時間ベースの処理に強みがあります。Kafkaとの統合や独自のストリーム処理アプリケーションを構築する際によく利用されます。
バッチも扱えるが本質はストリーム
Flinkは「ストリーム処理を基盤にバッチを扱う」という思想を持っており、イベント駆動アーキテクチャに最適化されています。ただしユーザーはFlink APIを直接利用する必要があり、OSS運用のコストも伴います。
Apache Beamの役割
モデルと抽象化レイヤー
Beamは「プログラミングモデル」であり、ランタイムそのものではありません。JavaやPythonで記述したBeamコードは「ランナー」を通して実行されます。代表的なランナーにはDataflow、Flink、Sparkなどがあります。(つまり、BeamコードはFlinkランナーで動かせる。)
Dataflowとの関係
Google CloudのDataflowはBeamを標準ランナーとして採用しており、ユーザーが書いたBeamパイプラインを自動的にスケーリング・最適化して実行します。このため試験で「Beamで書いたコードをDataflowで動かす」と説明されたら正しい理解です。
試験での判断基準
- 「Flinkを直接使う」選択肢が出た場合 → OSS運用の責任があるケース
- 「Beamを使う」選択肢が出た場合 → Dataflowなどランナーに抽象化して任せるケース
- 「バッチとストリームを統一的に扱う必要がある」→ Beam(Dataflow)
- 「OSSで低レイテンシのストリーム処理を作り込みたい」→ Flink
一次情報リンク:
- Beam: https://beam.apache.org/documentation/
- Flink: https://nightlies.apache.org/flink/flink-docs-stable/
- Dataflow: https://cloud.google.com/dataflow/docs/concepts/overview
実務と試験での整理の違い
実務では「既存のFlinkを運用している企業」と「Google Cloudに寄せてBeam+Dataflowを使う企業」が共存しています。試験問題では「マネージドか自前か」「抽象モデルかネイティブ実行か」が判断ポイントになります。Dataflowを答えにしたい問題は、必ず「運用負荷を減らす」「バッチとストリームを統一」といったキーワードが出てきます。
まとめ
Flinkはネイティブなストリーム処理エンジン、Beamは処理モデルの抽象化であり、DataflowはそのBeamランナーです。試験中に「どちらもストリーム処理じゃん」と混乱したときは、運用責任の所在と抽象度の違いを思い出してください。読了後は、Beam公式サイトの「Programming Guide」を一度確認し、バッチ/ストリーム統一モデルのイメージをつかんでおくと試験対応力が上がります。