この記事では、急速に進化するAIを脅威ではなく「最高の相棒」として活用するための思考法「トリプルシンキング」を、具体的なビジネスシーンの例を交えながら分かりやすく解説します。AIが得意な論理的思考(ロジカル)に加え、人間ならではの批判的思考(クリティカル)と水平的思考(ラテラル)を組み合わせることで、AIの分析力を最大限に引き出し、これまでにない価値を創造する方法を提案します。AI時代に自身の価値をさらに高めるためのヒントが満載です。
クラウドインフラの分野で事業を推進されている皆様、こんにちは。
最近の生成AIの進化には、目を見張るものがあります。専門的な質問を投げかけても、驚くほど的確な答えが返ってくることも珍しくありません。その能力を目の当たりにし、「私たちの仕事はこれからどうなるんだろう?」と、ふと考えさせられた経験はありませんか。
でも、大丈夫。結論から言うと、 AIは私たちの仕事を奪うんじゃなくて、仕事のやり方を劇的に変えてくれる「最高の相棒」 になるんです。ただし、それには一つだけ条件があります。それは、AIが決して持ち得ない、私たち人間ならではの「考える力」を磨き続けること。
本日は、その「考える力」を効果的に引き出すフレームワーク 「トリプルシンキング」 について、AIとの新しい関係性を模索する皆様と共に、深く掘り下げていきたいと思います。
AI時代の必須スキルセット「トリプルシンキング」とは?
「トリプルシンキング」とは、決して難解な理論ではありません。3つの異なる思考法を、状況に応じて適切に使い分けるためのアプローチです。ここでは、それぞれの思考法を個性的なキャラクターとして紹介します。
1.ロジカルシンキング(論理的思考)の「ロジック先生」
- 得意技:複雑なデータを分析し、「AだからB、BだからC」と物事を筋道立てて結論を導き出すこと。
- 特徴:矛盾を嫌い、一貫性のある構造を重視します。
- AIは、このロジカルシンキングが非常に得意です。膨大なデータから最適な答えを論理的に導き出す、まさに「ロジック先生」の集合体と言えるでしょう。
2.クリティカルシンキング(批判的思考)の「ナーゼ君」
- 得意技:「それは本当に正しいのか?」「そもそも、この前提は妥当か?」と物事の本質を深く問い続けること。
- 特徴:物事を鵜呑みにせず、常に健全な懐疑心を持ちます。
- AIが出した答えの信憑性や前提条件を冷静に評価する、思考の品質を守る重要な役割を担います。
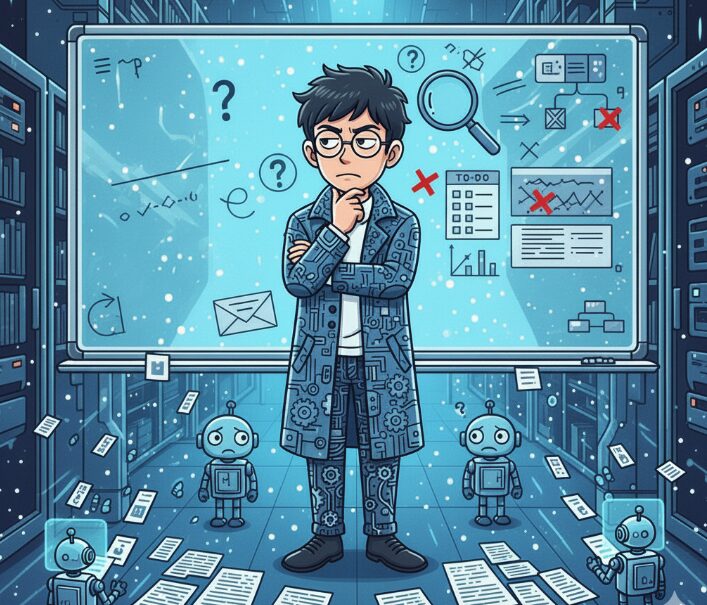
3.ラテラルシンキング(水平思考)の「ひらめき王子」
- 得意技:「もし、〜だったらどうだろう?」と常識の枠を超えた問いを立てること。
- 特徴:既存のルールや前提にとらわれず、全く新しい発想を生み出します。
- AIが過去のデータから答えを導き出すのに対し、まだデータのない未来や新しい可能性を探求するイノベーターです。

AI時代に人間が提供できる独自の価値は、まさに 「ナーゼ君(クリティカル)」 と 「ひらめき王子(ラテラル)」 の思考にあります。AIという強力な「ロジック先生」をいかにして活用し、この二つの思考と連携させるかを見ていきましょう。
ビジネスの現場で役立つユースケース2選
ここでは、ビジネスシーンで直面する具体的な課題を例に、トリプルシンキングの活用法を3つのステップで見ていきます。
ユースケース1:「チームの生産性を向上させたい」(業務改善)
課題:「チームのプロジェクトが慢性的に遅延しており、コミュニケーションにも課題を感じる。生産性を抜本的に改善したい」
❌ やりがちな失敗例
表面的な対策(会議を増やす、新しいツールを導入する等)に終始し、根本原因が未解決のままメンバーの負担だけが増加してしまう。
👍 トリプルシンキング活用例
Step 1:【クリティカルシンキング】「ナーゼ君」が問いを立てる
「生産性が低い」という曖昧な問題を、具体的な問いに分解します。
- 「生産性が低いとは、具体的にどういう状態か?アウトプットの量か、それとも手戻りの多さか?」
- 「コミュニケーションは”量”が不足しているのか、それとも”質”に問題があるのか?」
Step 2:【AIとの協業】「ロジック先生」にボトルネックを特定させる
本質的な問いを立てた上で、客観的なデータ分析をAIに実行させます。
- プロジェクト管理ツールのタスクデータを分析させ、どの工程でリードタイムが長期化しているかを特定させる。
- プロンプト例:
「過去3ヶ月分のプロジェクトチャットログを分析し、『仕様確認』『〇〇さん待ち』という単語が含まれる会話の頻度と、その会話が集中している時期を特定してください」
Step 3:【ラテラルシンキング】「ひらめき王子」がひらめく
AIが特定した客観的なボトルネックに基づき、従来の常識にとらわれない改善策を発想します。
- 「定例会議を廃止し、テキストベースの非同期コミュニケーションを原則としてはどうか?」
- 「週に一度、業務を一切行わずドキュメント整理と自己学習に集中する日を設けることで、長期的な生産性を高められないか?」
このケースで重要なのは、「感覚的な課題」を「客観的なデータ」に変換するプロセスです。「生産性が低い気がする」という感覚は、それだけでは精神論に陥りがちです。しかし、クリティカルシンキングで「そもそも生産性とは何か」という問いを立て、AIというツールで具体的なボトルネックを可視化することで、初めてチームは建設的な議論をスタートできます。AIが示したデータに基づき、人間が「常識を疑う」ことで、真に効果的な解決策が見えてくる良い例だと考えます。
ユースケース2:「AIを活用した新サービスを企画せよ」(新規企画)
課題:「競合他社がAIを活用した新機能をリリースし、市場で評価されている。当社も対抗しうる新サービスを企画する必要がある」
❌ やりがちな失敗例
競合の模倣に終始し、明確な差別化要因を打ち出せない。自社の顧客が本当に求めている価値から乖離した、機能ありきの企画になってしまう。
👍 トリプルシンキング活用例
Step 1:【クリティカルシンキング】「ナーゼ君」が問いを立てる
「AIで何か作れ」という指示の裏にある、本質的な目的を探ります。
- 「そもそも、顧客は競合のAI機能の何に価値を感じているのか?それによって、どのような課題が解決されているのか?」
- 「AIの活用が目的化していないか?AI以外の手段で、よりシンプルに顧客の課題を解決する方法はないか?」
Step 2:【AIとの協業】「ロジック先生」に市場を分析させる
本質的な問いを、AIを使ってデータで裏付けます。
- SNSやニュース記事、顧客からのフィードバックなど膨大なテキストデータを分析させ、顧客の潜在的なニーズを抽出させる。
- プロンプト例:
「添付の顧客アンケート自由記述欄500件を分析し、特に『時間の無駄』『面倒』といった感情に関連するキーワードを抽出し、TOP5を教えてください」
Step 3:【ラテラルシンキング】「ひらめき王子」がひらめく
AIの分析結果から、競合とは異なる新しいサービスの切り口を発見します。
- 「競合がカバーしていない、よりニッチな顧客課題に特化したサービスは考えられないか?」
- 「完全自動化ではなく、あえて専門家が最終チェックを行う『半自動AIサービス』として、信頼性や安心感を付加価値にできないか?」
ここでのポイントは、「競合追随」という思考停止から脱却する点にあります。ビジネスの現場では、つい競合の動きに目が行きがちですが、本当に見るべきは自分たちの顧客です。クリティカルシンキングは「本当に戦うべき場所はそこで正しいのか?」と問い直し、AIは顧客自身も気づいていないような潜在的なニーズをデータから示唆してくれます。その客観的なインサイトを基に、人間ならではのラテラルシンキングで独自の価値を創造する。これこそがAI時代の正しいサービスの作り方ではないでしょうか。

思考の順番は?効果を最大化するサイクル
これら3つの思考は、どの順番で使えば効果的なのでしょうか。
結論から言うと、決まった一方通行の順番はありません。 むしろ、それぞれの思考を状況に応じて行ったり来たりさせる 「サイクル」 として捉えることが重要です。 ただし、このサイクルを始動させる上で、最も効果的な「スタート地点」があります。それは…
最初に「ナーゼ君(クリティカル思考)」を登場させること。
なぜなら、これは事業やプロジェクトにおける「目的地の設定」そのものだからです。もし最初に向かうべき方角を間違えてしまえば、どんなに高性能な分析(ロジカル)を行い、どんなに斬新なアイデア(ラテラル)を出したとしても、望む成果にはたどり着けません。「そもそも、我々が解決すべき本当の課題は何か?」と、最初に取り組みの軸を正しく定めることが、成功の鍵を握るのです。

【思考のサイクル(一例)】
- ナーゼ君 (クリティカル) が「本当の課題は何か?」と本質を問う。
- ひらめき王子 (ラテラル) が「こんな解決策はどうか?」と常識を超えた仮説を立てる。
- ロジック先生 (ロジカル) が「その仮説を検証する筋道とコストは?」と具体的に分析する。
- 再び ナーゼ君 (クリティカル) が「この計画で、当初の課題は本当に解決されるのか?」と妥当性を評価する。
このサイクルを、3つの異なる視点から対話するように、頭の中で回していくことが重要です。
まとめ:AIと共に、思考の舵を取る
AIの進化は、私たちが「考える」という行為そのものから離れることではありません。むしろ逆です。定型的で時間のかかる分析作業をAIに委ねることで、私たち人間は、より本質的で、創造的な「思考」に集中できる時間を手に入れるのです。
クリティカルシンキングで、進むべき道が本当に正しいかを常に検証し、
ラテラルシンキングで、誰も思いつかなかった新しい可能性を見出し、
ロジカルシンキングで、AIという強力な分析エンジンを的確に使いこなす。
トリプルシンキングとは、AIというパートナーを得た私たちが、自らの思考をより高いレベルでコントロールするための思考のフレームワークです。
AIの能力を最大限に引き出すのは、最終的には人間の思考です。この新しい時代の舵を握るのは、私たち自身です。トリプルシンキングという思考術を手に、AIと共に、まだ見ぬ価値ある未来を創造していきましょう。

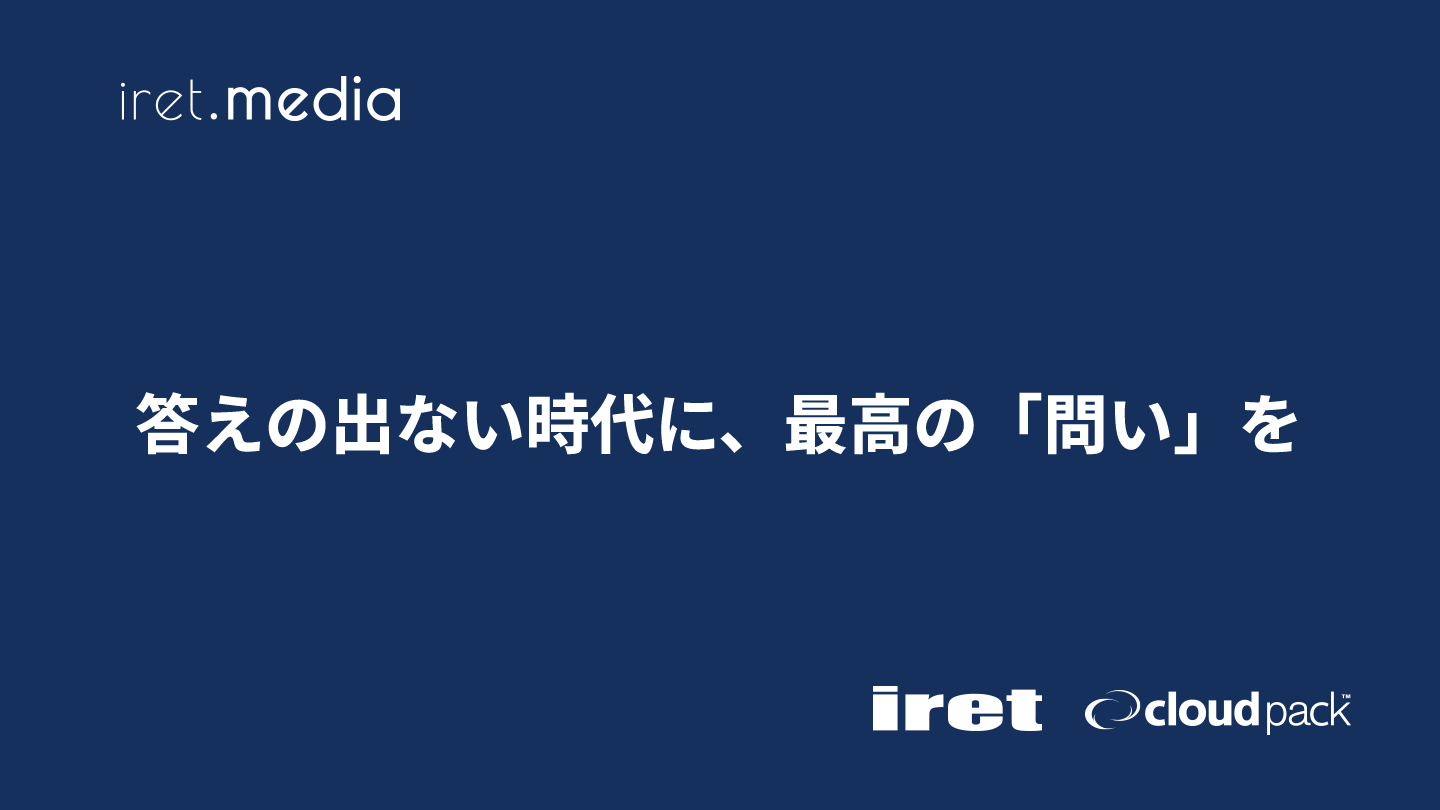
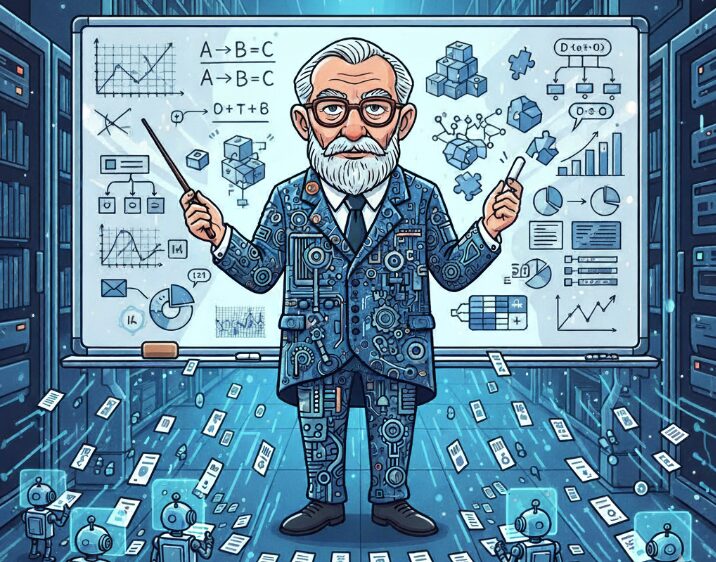
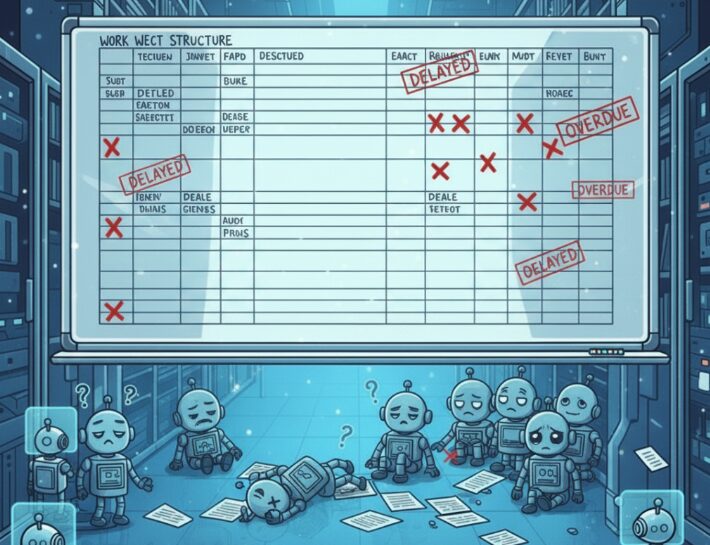

![【AWS re:Invent 2023】Amazon CloudWatch natural language query generationがプレビュー発表されました[COP227-INT]](https://iret.media/wp-content/uploads/2023/08/reinvent2023-220x110.png)

