こんにちは。デザイン事業部の田村です。選択アーキテクチャという言葉を聞いたことはありますでしょうか。UX検定基礎の資格勉強をする中で知ったキーワードについて関連するものとともにご紹介します。
1日の選択回数
突然ですが、1日にどれだけ多くの選択をしているかを考えたことはありますか?「今日は何を着よう」「どこへ行こう」「何を食べよう」「どの道を通ろう」今日1日だけでも思い当たる選択の場面は多いのではないでしょうか。ケンブリッジ大学の研究によると、私たちは1日に最大3万5,000回の決断をしています。小さなものから大きなものまで、これらの選択は私たちの日常生活の一部となっており、その都度、私たちの脳はエネルギーを消費しています。一見、意識的に行っているように思えるこれらの選択も、実は多くの場合、無意識的に影響を受けています。この影響を理解して無意識に行う選択をより良い選択に繋げるために今回は「選択アーキテクチャ」と「ナッジ理論」、それらに関連するキーワードについて具体例と共にご紹介していきます。

選択アーキテクチャ(Choice Architecture)
選択アーキテクチャとは、選択肢がどのように提示されるかによって、私たちの行動や意思決定がどれほど影響を受けるかを考える理論です。例えば、スーパーで健康的な野菜を目立つ場所(視線の高さや必ず通る通路沿い)に配置すると、
消費者は自然と健康的な食材を選びやすくなります。逆に、ジャンクフードが目立つ場所に置かれていると、消費者はそれを選びがちです。このように、選択肢をどう提示するかが、私たちの意思決定を大きく変えることを意味します。

選択アーキテクチャは、無意識的に私たちの意思決定を誘導する方法です。例えば、コーヒーに入れる砂糖の量を減らすために、スプーンのサイズを小さくするだけで、砂糖の使用量を減らすことができるという事例もあります。このように、小さな変更が私たちの健康に大きな影響を与えることがあります。
ナッジ理論
ナッジは「nudge:そっと後押しする」と言う意味があります。
親ゾウが子ゾウを鼻でそっと押すように人々が自分自身にとってより無意識のうちにでも良い選択をするように手助けする手法です。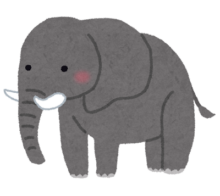 行動経済学者リチャード・セイラーとキャス・サンスティーンが著書『Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness(ナッジ: 健康、富、幸福に関する意思決定の改善)』で広められたとされています。
行動経済学者リチャード・セイラーとキャス・サンスティーンが著書『Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness(ナッジ: 健康、富、幸福に関する意思決定の改善)』で広められたとされています。
ナッジ理論についてのフレームワークやさまざまな具体例については別記事でご紹介していますので是非ご参照ください。
ナッジ理論について
https://iret.media/103074
ナッジ理論の特徴
ナッジ理論の特徴は、私たちが無意識に行動する際に認知バイアス(思い込みや偏り)を利用して、選択の自由は残しつつ選択肢を目立たせることです。例えば、公共料金の支払期限が近づくと、「延滞料が発生します」という通知を送ることで、消費者が支払いを促されるといった仕組みです。これは強制するのではなく、無理なく行動を促す方法です。
(良い)ナッジと悪いナッジ(スラッジ)
ナッジには、「良いナッジ」と「悪いナッジ(スラッジ)」の2種類があります。
良いナッジは、人々がより良い選択をするように軽い促しや小さな非強制的介入を通じて、有益な決定に導く方法です。一方、悪いナッジとされる「スラッジ(sludge:泥、ぬかるみ)」はその反対で、賢い意思決定や望ましい行動を難しくし、時にはスラッジを作成する組織の利益のために設計されています。例えば、サブスクリプションの解約手続きが非常に面倒で、消費者が手続きを諦めて契約を続けるような場合です。

アプリでの活用例
ナッジ理論は、アプリの設計にも活用されています。
例えば、新機能がリリースされたとき、アプリのユーザーインターフェース(UI)を工夫することで、ユーザーがその機能を使いやすくなります。機能の使い方をステップバイステップで紹介したり、通知を使って新機能を強調することで、ユーザーは自然にその機能を試すようになります。
これにより、アプリのユーザーは新しい機能を簡単に活用でき、アプリの利便性や満足度が向上します。ユーザーにとってストレスが少なく、自然に新しい行動を促すことができます。
選択アーキテクチャとナッジ理論の違い
ナッジ理論は選択アーキテクチャ内の特定の戦略です。
スーパーで例えると、選択アーキテクチャは、スーパーの全体的なレイアウトとデザインとしたら、ナッジ理論は、店内で選択に影響を与えるために使用される戦略です。特定の商品を目の高さに置いたり、買い物客が牛乳や卵などの必需品を手に入れるために目を惹かれがちなお菓子コーナーを見過ごさせる戦略がナッジ理論です。
その他の関連キーワード
関連するキーワードについてご紹介します。
デフォルト設定:ユーザーが特に選択しない限り、自動的に選択される設定やオプション。選択を促すことなく、あらかじめ設定されたオプションが適用される設定です。
例えば、サービスの契約時に「自動更新」がデフォルトになっていると、多くの人がそのまま自動更新を受け入れてしまいます。自分で選択肢を変更しない限り、契約が更新され続ける仕組みです。選択肢を変更しない限り、意識的に選んだつもりでも実はデフォルトに従っていることになります。
認知バイアス:人々が情報を処理する際に無意識的に生じる偏り。
認知バイアスの一種の確証バイアスの一例をご紹介します。
SNSでは、アルゴリズムがユーザーの過去の行動や関心に基づいてコンテンツを表示するため、自分の考えに合った情報が目立ちやすくなります。その結果、自分が信じていることを裏付ける情報ばかりを見て、無意識のうちに特定の方法で情報を解釈したり、反対の意見を無視することがあります。情報を処理する際に生じる系統的な偏りのこと。無意識のうちに特定の方法で情報を解釈したり、判断を下したりし、これが誤った結論を引き起こすことがあります。
限定合理性:完璧な選択をするのではなく、「十分に良い」選択をすること。時間、情報、精神的リソースに制約があるため、最良の選択ではなく十分に良い選択を行うことが一般的です。
例えば、何か買い物をする際にできるだけいいものを選びたい気持ちはありつつ、時間/情報/精神的リソース等にはどうしても限りがあるため、最も安くて性能がいいものを選ぶのではなく、予算内で「これで十分」と思える車を選択した経験がある方は多いのではないでしょうか。この選び方は限定合理性に該当します。
プロスペクト理論:損失が利益よりも強く感じられる、利益を得るよりも損失を避けることを優先する傾向があるという理論です。
例えば、ある人が、100万円を確実に得られる賭けと、50%の確率で200万円を得られる賭けを選ぶ場面を想像してみてください。プロスペクト理論では、人は100万円を確実に得る選択を好むと予測されます。なぜなら、確実な利益を好み、リスクを避けるからです。
アンカリング効果
最初に提示された情報(例えば価格や数値)が、その後の判断に強い影響を与える心理的現象。「最初の情報」が基準(アンカー)となり、後の判断を引き寄せます。
例えば、腕時計が「定価30,000円」のところ、「今なら20,000円!」で販売されていると、最初に「30,000円」という高い価格が示されることで、消費者は「20,000円」がとてもお得に感じます。実際にはその時計が最初から20,000円で売られていた場合と比べると、お得感は大きく異なります。最初に高い価格が提示されることで、価格が安く感じられる現象です。
まとめ
ナッジ理論と選択アーキテクチャは、私たちの意思決定に大きな影響を与えるものです。普段の生活を振り返ってみると思い当たる場面は多いのではないでしょうか。無意識に行う選択をより良い方向に導くために、選択肢の提示方法や環境設計を工夫することが重要です。ナッジ理論を適切に活用することで、より良い選択を行いやすくなります。日々の生活やビジネス、アプリの設計において、この理論をうまく活用することで、賢い選択、より良い生活へつながるのではないでしょうか。サービスに関わる際にどうすればユーザーが最適な選択肢を選びやすくなるのか、悪い体験ではなく、より良い体験につながるかを考え続けていこうと思います。ここまでお読みいただきありがとうございます。
参考
https://www.kaonavi.jp/dictionary/nudge/
https://talknote.com/magazine/nudge-theory/
https://insidebe.com/articles/choice-architecture/
https://whatfix.com/blog/nudge-theory/
https://www.imperial.ac.uk/nudgeomics/about/what-is-nudge-theory/



