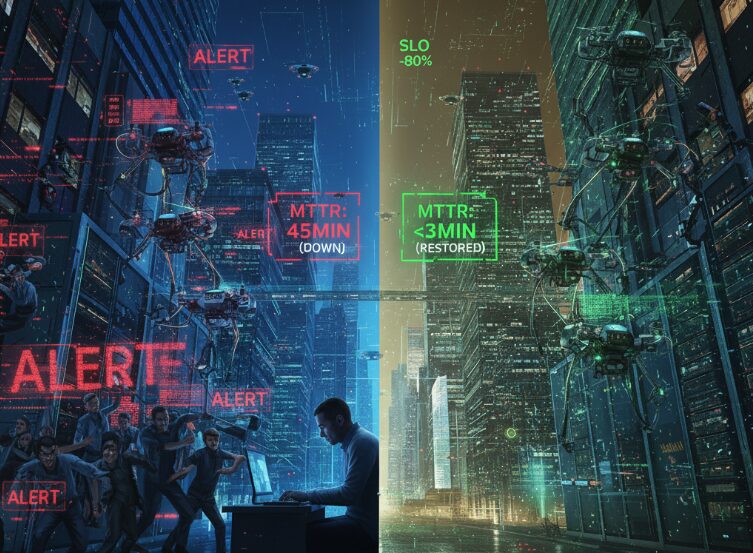はじめに
生成AI(特にClaude)を使ったプロジェクトで、プロンプトの精度をあげるコツを12個例文つきでまとめてみました。
サクッと使ってみて、自分のPJに合った改善案を試してみてください。
目次
1.プロンプトジェネレーターを活用する
2.明確かつ直接的に指示する
3.マルチショット(複数例)プロンプト
4.AIに考えさせる(思考の連鎖)
5.XMLタグを使用する
6.役割を割り当てる(システムプロンプト)
7. 回答を事前入力する(応答をプリフィル)
8.複雑なプロンプトを連鎖させる
9. 長文テキスト処理のコツ
10.プロンプトテンプレートを使用する
11.プロンプト改善ツール
12 拡張思考プロンプトのコツ(発散→収束)
本題
1) プロンプトジェネレーターを活用する
狙い:モデルに“良い指示”を作らせる(要件の穴を先に塞ぐ)。
コツ:用途・制約・出力形式・評価基準を質問させ、改良案を返させる。
例文
NG 社内メンテ告知文を作って。 OK あなたはプロンプト設計士。下記タスクの最適プロンプトを作る。 1) 不明点を最大5問だけ私に質問→私の回答を待つ 2) 回答後、「最終プロンプト」「チェックリスト」「サンプル入出力」を出力 タスク: 社内向けAPIメンテ告知を作成(日時/影響/連絡先明記)
効果:タスクに最適化された高品質プロンプトを手早く得られる。
理由:モデルに要件・制約・出力形式の穴埋め質問と整形を自己実行させるから。
2) 明確かつ直接的に指示する
狙い:曖昧語を減らし、完成形の要件を列挙。
コツ:「目的/読者/制約/禁止/出力形式/採点指標」。
例文
NG 丁寧にまとめてください。 OK 目的: 社内APIメンテ告知を300±30字で作成 読者: 開発部/CS 必須: 日時・影響範囲・問い合わせ先・リンク 禁止: 比喩/絵文字 形式: Markdown(H3見出し→本文→箇条書き3点)
効果:出力のブレが減り再現性と精度が上がる。
理由:目的・読者・制約・形式・禁止事項を明示して探索範囲を狭めるから。
3) マルチショット(複数例)プロンプト
狙い:望む“変換規則”を例で教え込む。
コツ:短い入出力対を2–3組→「新しい入力」を提示。
例文
NG この文を敬体にしてください。 OK # 例 入力: すぐ返事ください → 出力: ご返信をお願いできますでしょうか。 入力: ちょっと見てほしい → 出力: ご確認いただけますと幸いです。 # 新しい入力 入力: 早めに対応して → 出力:
効果:望む文体や変換規則が安定して再現される。
理由:入出力ペアが強い条件付けとなりパターン学習を促すから。
4) AIに考えさせる(思考の連鎖)
狙い:いきなり結論より、前提→選択肢→評価→結論の順に。
コツ:「中間の要点だけ可視化(箇条書き)」を指定。
例文
NG どの告知文が良いか選んで。 OK 次の順で回答: 1) 前提3点 2) 選択肢と長所/短所(各1行) 3) 結論(理由3つ) 課題: 社内APIメンテの伝達方法(Slack/メール/社内Wiki)
効果:複雑課題でも論理的で妥当性の高い結論が出やすい。
理由:中間推論を外化し自己チェックと誤り検出の機会を増やすから。
5) XMLタグを使用する
狙い:データと指示の境界を明確にする。
コツ:タグで属性を分離。
例文
NG この長文を5行で要約して重要語は強調して。 OK <instructions>5行要約。重要語に**を付ける。固有名詞は保持。</instructions> <data>[ここに長文]</data> <format> - 要点1 - 要点2 - 要点3 - 要点4 - 要点5 </format>
効果:指示・データ・出力仕様の混線が減りミスが減る。
理由:構造化でコンテキスト境界が明確になりパース可能性が上がるから。
6) 役割を割り当てる(システムプロンプト)
狙い:「誰として振る舞うか」で出力品質が上がる。
コツ:スキル/口調/境界(やらないこと)を明記。
例文
NG Wiki記事っぽく整えて。 OK あなたは社内テクニカルライター。口調は穏やかな敬体。推測で事実を作らない。 下記メモを社内Wiki記事に整形(見出し/表/注意点): [メモ本文]
効果:口調と視点が一貫し専門的な出力になりやすい。
理由:役割・権限・禁止行為を先に定義して行動方針を固定できるから。
7) 回答を事前入力する(応答プリフィル)
狙い:雛形や第一段落を下書きとして与え、続きを書かせる。
コツ:
例文
NG
この告知を良くして。
OK
最小テンプレ(コピペ)
下書きを推敲・完成してください。事実・数値・日時は変更不可、未知は「要確認」と明示。
要件:
- 文字数: {{length}}字(±10%)
- 文体: {{tone}}(例: 丁寧な敬体)
- 必須要素: {{musts}}(例: 日時/影響/連絡先)
- 出力形式: {{format}}(例: Markdown, 見出しH3→本文→箇条書き3点)
<assistant_draft>
{{your_draft_text}}
</assistant_draft>
埋め例(APIメンテ告知)
下書きを推敲・完成してください。事実・数値・日時は変更不可、未知は「要確認」。
要件:
- 文字数: 300字
- 文体: 丁寧な敬体
- 必須要素: 日時/影響/連絡先
- 出力形式: Markdown(H3→本文→箇条書き)
<assistant_draft>
結論: 今回のメンテは互換性維持。日時: 2025-09-28 22:00-24:00。
影響: リクエストの一部で5xxが増える可能性。再試行で回復見込み。
問い合わせ: #api-ops
</assistant_draft>
効果:望む骨子・トーンに沿った続きを高確率で引き出せる。
理由:下書きが強力なコンテキストとなり生成の着地点を誘導するから。
8) 複雑なプロンプトを連鎖させる
狙い:大仕事を「設計→ドラフト→検証→最終」の段階に分ける。
コツ:各ステップで出力物と評価基準を固定。
NG 仕様書を完成させて。 OK Step1=要件抽出: 本文から必須要件/未確定点/リスクを箇条書きで。私の確認待ち。 Step2=骨子: 見出し案と各要約(2行)、要件を満たすこと。未確定点はTODO化。 Step3=本文: 800±100字、表1つ、チェックリスト付き。 本文: [企画メモ]
効果:大きな仕事を品質担保しつつ段階的に完成できる。
理由:各段で成果物と評価基準を固定し早期に誤差修正できるから。
9) 長文テキスト処理のコツ
狙い:分割→要約→抽出→変換のパイプライン化。
コツ:トークン節約、禁止事項、見出しごとの処理。
例文
NG このレポートを要約して。 OK 手順: 1) 章ごとに200字要約 2) KPIと数値を抽出して表化(指標/値/期間/出所) 3) 重要示唆を100字で 禁止: 直接引用は40字以内、数値の創作禁止 <text>[長文]</text>
効果:要点抽出と構造化が安定しトークン超過も回避できる。
理由:分割→要約→抽出→変換のパイプラインで負荷を分散するから。
10) プロンプトテンプレートを使用する
狙い:繰り返し作業を変数で回せる形に。
コツ:{{purpose}} {{audience}} {{length}} {{style}} など。
例文
NG
採用求人の紹介文を書いて。
OK
最小テンプレ(コピペ)
目的: {{purpose}}
読者: {{audience}}
長さ: {{length}}字(±10%)
文体: {{tone}}
必須: {{musts}}
禁止: {{prohibits}}
出力形式: {{format}} # 例: Markdown(H3→本文→箇条書き3)
評価: {{rubric}} # 例: 正確性/簡潔性/体裁を各0-2点で
素材テキスト:
{{input_text}}
埋め例①(APIメンテ告知)
目的: 社内向けAPIメンテの周知
読者: 開発部/CS
長さ: 300
文体: 丁寧な敬体
必須: 日時/影響/問い合わせ先
禁止: 絵文字/比喩
出力形式: Markdown(H3→本文→箇条書き3)
評価: 正確性/簡潔性/体裁(各0-2)
素材テキスト:
日時=2025-09-28 22:00-24:00、影響=一時的に5xx増、連絡=#api-ops
埋め例
purpose=社内通知, audience=開発部, length=300, style=丁寧, format=Markdown
効果:再現性と生産性が上がり品質のばらつきが減る。
理由:変数化により同一構造を使い回ししやすくなるから。
11) プロンプト改善ツール
狙い:プロンプトをテスト→評価→改修のループで強化。
コツ:簡易でも評価ルーブリックを作る。ペア比較も有効。
例文
NG
もっと良くして。
OK
下記出力を基準で0-2点採点し、改善点3つと改稿版を返す。
基準: 正確性/簡潔性/再現性/体裁
対象出力: [前回の告知文]
返す形式: {総合点, 改善点, 改稿}
(ツール例:テスト用のCSV+評価プロンプト、promptfoo/LangChain等でもOK)
効果:出力品質を反復的にチューニングできる。
理由:ルーブリック評価やAB比較で具体的な改善点を定量把握できるから。
12) 拡張思考プロンプトのコツ(発散→収束)
狙い:発散(複案提示)→収束(選定理由と最終案)を1プロンプトで。
コツ:選定基準を先に固定、反証と失敗時のプランBも出す。
例文
NG メンテ周知のベストプランを教えて。 OK 発散: 3案(保守/攻め/折衷)を各1行で[コスト/効果/リスク]付き提示。 収束: 基準(リードタイム≤2週, 誤配信リスク小)で最良1つと理由3行。 反証: 採用しなかった案の最大の利点を各1行。
効果:代替案比較を経て納得度の高い最終案に到達できる。
理由:選定基準と反証を明示しバイアスを抑えて意思決定できるから。
仕上げのチェックリスト(汎用)
- 目的・読者・制約・形式・禁止が明文化されている
- 入出力例がある(マルチショットは特に)
- 評価/採点の観点がある(自己改善を促す)
- 長文は段階処理(分割→要約→抽出→最終)
- 最後に“足りない前提は?”を必ず質問させる
関連記事
この記事を作成するにあたって、参考にさせてもらった記事です。
本稿は自身にとって必要な情報を整理しまとめ直したものなので、
よければ元記事もご確認ください。
https://qiita.com/Nakamura-Kaito/items/22303be7122e5e8abe2a