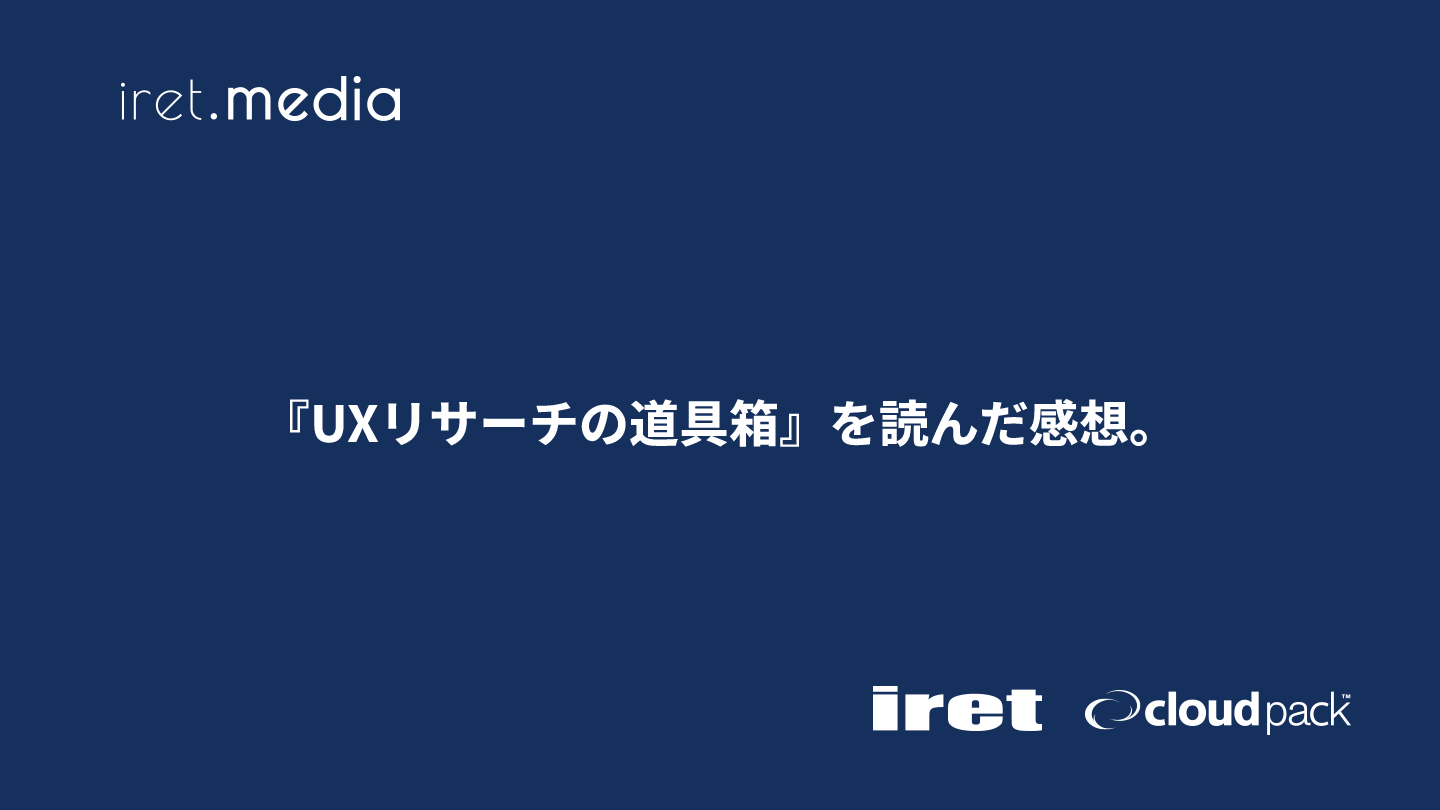こんにちは。アイレット デザイン事業部でディレクターをしている ivanov です。
私のキャリアはテスティングエンジニア(QA)からスタートしました。その後、市場調査 → サービス企画 → 経営企画 → Webデザイナー → グロースハッカー → プロダクトデザイナー → ディレクター(現在)と、自分で言うのもなんですが、なかなか珍しい経歴を辿ってきたと思います。最近は、0→1でサービスをデザインし、開発チームに橋渡しをするような役割を担うことが増えてきました。
テスティングエンジニアからグロースハッカーだった頃までは、日常的に定量的なデータ分析を中心に業務を進めていましたが、サービス企画や経営企画を経験する中で、徐々に定性的な分析の重要性も感じ、定性データも扱うようになりました。昨今のUXデザインの盛り上がりとともに、インタビューなどの定性的リサーチに触れる機会も増え、「リサーチとは何か?」を改めて考えるようになった今日この頃です。
そんな中、SNSでユーザーインタビュー事例の投稿を見かけたのですが、「ボタンの色は何色が好きですか?」「どんなデザインがいいですか?」といった質問の事例に違和感を覚えました。そこで、UXリサーチについて学び直してみようと思い、今回『UXリサーチの道具箱』を読んでみました。
『UXリサーチの道具箱』とは?
この本では、表面的な「ユーザーの声」ではなく、より深い「本質的なニーズ」に迫り、それを可視化・分析するための7つの手法が紹介されています。
- ユーザーインタビュー
- (定性的な)データ分析
- ペルソナ
- シナリオ
- ジャーニーマップ
- ジョブ理論
- キャンバス
インタビュー設計のポイントやデータ分析の方法、さらに理解を深めたい人に向けた参考書籍の紹介もあり、とても分かりやすい内容でした。
詳細はぜひ本書を読んでいただきたいのですが、簡単に内容と感想を書いていきます。
ユーザーインタビュー
ユーザー体験に潜む「暗黙のニーズ」を的確に捉え、それに対する解決策を提示することこそがプロフェッショナルの仕事であるという指摘は、まさにその通りだと納得しました。 そのために、ユーザーに弟子入りするような姿勢でユーザーの体験を深く理解する手法が紹介されており、具体的な質問のテクニックやインタビュー全体の設計方法についても触れられていました。
(定性的な)データ分析
私はこれまで定性的なデータも集計して分析していました。本書ではそのアプローチも有効であるとしつつ、KJ法を用いたグルーピングによって定性データを構造化し、そこから行動や思考のパターンを見出す手法が紹介されていました。
私はKJ法をデータ分析手法として認識していなかったため、この解説は大きな驚きでした。同時に、私自身がこの手法にしっくりきた理由や、KJ法を得意とする上司と相性が良い理由の一端が理解できたように思います。データ分析はスプレッドシートやRみたいなツールで統計的にやるものだというバイアスが私自身にかかっていたことに気がつきました。
ペルソナ
基本的なペルソナ作成法に加え、複数のペルソナ候補が生まれた場合の考え方や対応策が解説されていました。 私自身は複数のペルソナを策定する経験が少なく、「このクラスターには複数のペルソナが存在するのではないか」という状況で、どのように対応すべきか悩むことがありました。これまでは最終的にターゲットとするペルソナを一つに絞り込むアプローチを取っていましたが、本書で提案されている「ペルソナに優先順位を設ける」という考え方は、非常に腑に落ちました。
シナリオ
シナリオには「UXシナリオ」「記録シナリオ」「対話シナリオ」などの手法があることと、シナリオの設計方法として「課題シナリオ(Problem Scenario)」「作業シナリオ(Activity Scenario)」「情報シナリオ(Information Scenario)」「対話シナリオ(Interaction Scenario)」を使っての設計手法が書いてありました。
HCD(人間中心設計)にも「価値シナリオ(Value Scenario)」「行動シナリオ(Activity Scenario)」「操作シナリオ(Interaction Scenario)」からUIを設計する「構造化シナリオ法」という手法があるのですが、本書で紹介されているシナリオと構造化シナリオ法で用いるシナリオには、関連性を感じるものの内容的には差異があるように思えました。機会があれば両者を実践し、共通点と相違点を深く理解したいと考えています。
ジャーニーマップ
ジャーニーマップとは、ターゲットとなるペルソナの体験を時系列で追い、ペルソナとサービス提供者との接点(タッチポイント)におけるインタラクションを可視化する手法です。 私自身はこれまでスプレッドシートを用いて表形式でジャーニーマップを作成していましたが、本書でその方法も有効であると述べられていたため、安心しました。 その他、ユーザーストーリーマッピングについても紹介されていました。
ジョブ理論
ジョブ理論とは、「イノベーションのジレンマ」の著者として知られるクレイトン・クリステンセン氏が提唱したもので、「人々は特定のジョブ(用事・課題)を片付けるために製品やサービスを雇う(利用する)」という考え方です。この理論に基づいたビジネス発想法が紹介されていました。
一部のUXデザイナーが陥りがちな罠として、「優れた価値を創造すれば、そのサービスは自ずと市場に受け入れられる」という誤解があります。しかし実際には、デザインによって生み出された価値とビジネスとを効果的に結びつける必要があり、これは非常に困難な作業です。
キャンバス
では、創造した価値とビジネスをどのように結びつければよいのでしょうか。その手法の一つとして「ビジネスモデル・キャンバス」が挙げられます。また、「バリュープロポジション・キャンバス」はビジネスモデル・キャンバスから「価値の提案」と「顧客セグメント」を抜き出したものです。本書では、これらのキャンバスの作成方法に加え、その際に重要となる「ペイン(顧客の悩みや問題)」と「ゲイン(顧客の得るものや喜び)」という概念について解説されていました。
バリュープロポジション・キャンバスを書いた経験がある方はわかると思いますが、慣れないうちは「ペイン」と「ゲイン」を対の関係として捉えがちです。特にエンジニアさんとワークショップをやったりすると日常的な業務で行なっているMECE(相互に排他的かつ網羅的)の考え方が影響し、これらを対として網羅的に洗い出そうとする傾向があります。しかし本書では、「ペイン」と「ゲイン」の数は必ずしも一致する必要はなく、それぞれ独立して考えるべきであるという指針が示されており、私自身の経験とも合致しており(自分のこれまでのアプローチが間違っていなかったことが分かって)安心しました。
読了後には冒頭で触れたようなSNS上のユーザーインタビューに対する違和感への答えも得られ大変良かったです。UXリサーチの基礎を体系立てて学びたい方には、おすすめの一冊と言って良いと思います。
読了後に伝えたいこと
この本で紹介されているのは、あくまで「手法」であり、「絶対的な正解」ではありません。手法は目的を達成するためのツールであって、それ自体が答えを導き出すものではないからです。私自身の経験でも、例えばビジネスモデルキャンバスを完璧に埋めることができたからといって、新規事業が必ずうまくいくとは限りませんでした。
私がユーザーインタビューで知りたいのは、「ユーザーがどんな体験をしているか」そして「その体験にはどんな感情が含まれていて、それがどのようなスピードで伝わっているのか」です。『UXリサーチの道具箱』で紹介されている手法も活用しながら、表面的な答えにとどまらず、より深く「本当に知りたいこと」にたどり着けるようなリサーチを、これからも実践していきたいと思います。