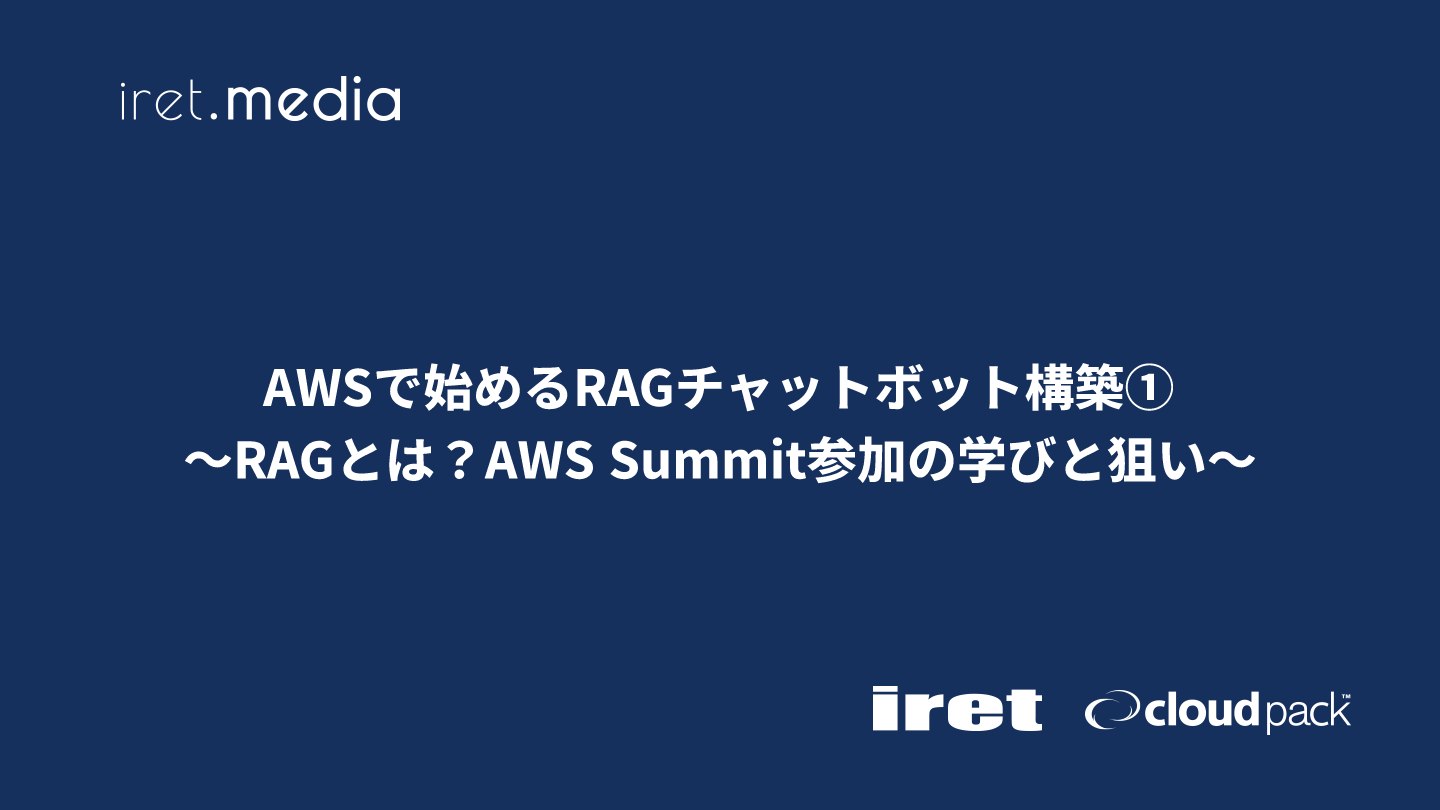はじめに
2025年6月に開催された AWS Summit Japan。生成AIを活用した最新のユースケースや、AWSの新サービスの発表など、多くの学びが得られるイベントでした。
私自身もエンジニアとしてこのイベントに参加し、特に印象に残ったのが「生成 AI のためのデータ活用実践ガイド」というセッションでした。
このセッションをきっかけに、RAG(Retrieval-Augmented Generation) というアプローチに改めて注目し、実際にAWSを使ってRAGチャットボットを構築することにしました。
この記事では、RAGとは何か、なぜAWSで構築しようと考えたのか、そして本シリーズの構成についてご紹介します。
AWS Summit Japan 2025 で得た気づき
生成AIは「活用のための土台」が問われるフェーズへ
今回のAWS Summitでは、生成AIのモデル自体よりも「どう活用するか」「どんなデータで強化するか」にフォーカスが移っている印象を強く受けました。
中でも注目したセッションがこちらです。
- セッション名: 生成 AI のためのデータ活用実践ガイド
- キーワード: 「非構造データ」「検索強化生成(RAG)」「Bedrock × OpenSearch」「文脈の重要性」
このセッションでは、「企業独自の知見を活かすためのAI活用には、社内のナレッジや文書をどう連携させるかがカギ」であるというメッセージが繰り返されていました。
RAGとは?
RAG(Retrieval-Augmented Generation)は、外部の情報検索を行ったうえで、生成AIが回答を行うアーキテクチャです。
従来の大規模言語モデル(LLM)は、あらかじめ学習された知識に基づいて応答を行うため、以下のような課題がありました。
- 最新情報に対応できない
- ユーザー固有の情報(社内ドキュメントなど)を反映できない
RAGはこの課題を解決するために、以下のような流れで処理を行います。
- ユーザーの質問をベクトル化
- OpenSearchなどの検索エンジンで、関連文書をベクトル検索
- 検索結果をもとに、生成AIが応答を構築
これにより、「ユーザーの質問に対して、社内の非構造データを活用した回答」が可能になります。
なぜAWSでRAGを構築しようと思ったか?
RAGを実装するには、以下のような機能が必要です。
- ベクトル検索ができるデータストア(例:OpenSearch)
- ユーザーの質問や状況を保存する仕組み(例:DynamoDB)
- ドキュメントの管理やアップロード(例:S3)
- テキストをベクトル化・応答生成できる生成AI(例:Bedrock + ClaudeやTitan)
これらがすべて AWSのマネージドサービスで揃う という点に魅力を感じました。
加えて、LambdaやCDKといったインフラ自動化・Serverlessアーキテクチャとの相性が良いのも大きな理由です。
今後の連載の構成(予定)
本シリーズでは、以下のような流れで「AWS上にRAGチャットボットを構築する方法」をご紹介します。
【第1回】(この記事)
RAGの概要と構築の動機
【第2回】
構成設計と使用サービス紹介(OpenSearch / DynamoDB / Bedrockなど)
【第3回】
PDFのインデックス処理の実装
S3からPDFを読み込み → テキスト抽出 → チャンク分割 → ベクトル化 → OpenSearchへのインデックス登録
【第4回】
RAG検索と回答生成の実装
ユーザー情報取得 → 質問のベクトル化 → 類似ドキュメント検索 → プロンプト構築 → Claudeによる応答生成
【第5回】
AWS CDKによるインフラ構築
IAMロール、S3、DynamoDB、OpenSearch、Lambda、API Gatewayをコードで管理
【第6回】
デプロイと動作確認
実際のデプロイ手順、サンプルデータ投入、テスト実行、全体の振り返り
まとめ
生成AIは「使い方」が問われるフェーズに入りました。そしてRAGは、まさにその鍵となる技術の一つです。
AWS Summitでの学びをきっかけに、実際に自分の手でRAGチャットボットを構築したプロセスを、これから数回にわたって紹介していきます。
次回は、どのような構成でRAGを実現するか、各AWSサービスの役割と選定理由について詳しく掘り下げていきます。